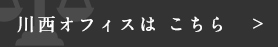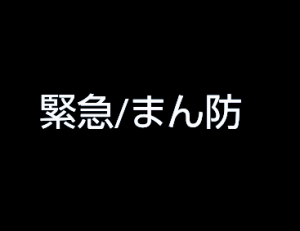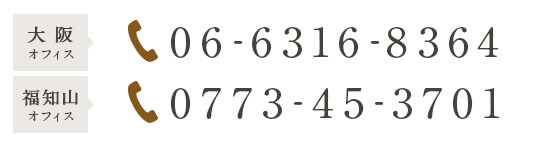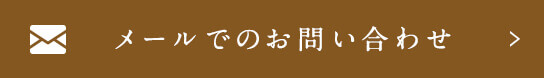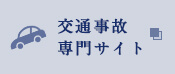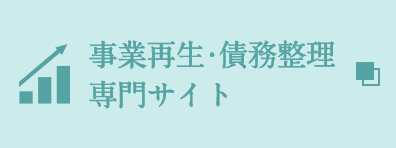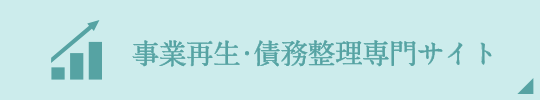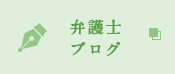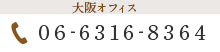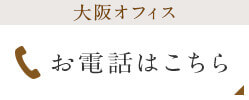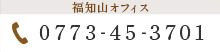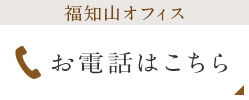- HOME
- 不動産
不動産関連③賃貸業と改正民法・原状回復
2021.05.10

1 原状回復関連の改正民法の概要は、以下のとおりです。
民法621条
賃借人は、賃貸物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃貸物の損耗並びに賃貸物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)賃借人は、期間満了後、賃貸物の返還義務を負い(616条、597条1項)その内容として原状回復義務を負うとされています(598条は、賃借人からみた収去「権」と位置付けます。)。
(2)ただ、その際の通常損耗や経年変化の取り扱いが明確ではありませんでした。判例上は、通常損耗や経年変化について、賃借人は原状回復義務を負わないとされ、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」でも同様の考え方がとられていました。改正民法では、これらを明文化しました。
2 原状回復関連事項を契約書で定める場合の検討
(1)標準契約書における原状回復関連事項は、以下のとおりです。
(明渡し時の原状回復)
第15条 乙は、通常の使用に伴い生じた本物件の損耗及び本物件の経年変化を除き、本物件を原状回復しなければならない。ただし、乙の責めに帰することができない事由により生じたものについては、原状回復を要しない。
2 甲及び乙は、本物件の明渡し時において、契約時に特約を定めた場合は当該特約を含め、別表第5の規定に基づき乙が行う原状回復の内容及び方法について協議するものとする。
そして、上記別表には、原則的な「原状回復条件」が定められた上で「例外としての特約」を記載することができるよう空欄が設けられています。
1項は、改正民法の規定に従った原則的な取扱いを示します。ちなみに、別表で貸主の負担されている主なものは、以下のとおりです。一般的に、通常損耗とされているものを水色、経年変化とされているものを紫色で示します。
① 床
畳の表替え等(次の入居者確保のためのもの)
フローリングのワックスがけ
家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡
畳の変色、フローリングの色落ち(日照、建物構造欠陥により発生)
② 壁・天井
テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(電気やけ)
壁等の画鋲、ピン等の穴
エアコン設置による壁のビス穴、跡
クロスの変色(日照などによるもの)
③ 建具等、ふすま、柱等
網戸の張替え(次の入居者確保のため)
網入りガラスの亀裂(構造による自然発生)
④ その他
専門業者による全体のハウスクリーニング(借主が通常清掃を実施)
エアコンの内部洗浄(喫煙等の臭い付着なし)
消毒(台所・トイレ)
浴槽、風呂釜等の取替え(次の入居者確保のため)の
鍵の取替え(鍵紛失等のない場合)
設備機器の故障、使用不能(機械の寿命)
(2)民法621条は任意規定であり、特約による変更は可能ですが、公序良俗や消費者契約法等に違反しないこと必要であることは、修繕等や一部滅失等による賃料減額のところで、述べたとおりです。そして、例えば、標準契約書において「例外としての特約」を交わす場合の注意点は、以下の点です。
ア 明確な合意
最2小判平成17年12月16日判タ1200号127頁(以下、平成17年判決といいます。)は「賃借人は、賃貸借契約が終了した場合には、賃借物件を原状に回復して賃貸人に返還する義務があるところ、賃貸借契約は、賃借人による賃借物件の使用とその対価としての賃料の支払を内容とするものであり、賃借物件の損耗の発生は、賃貸借という契約の本質上当然に予定されているものである。」とした上で、建物の賃借人に通常損耗についての原状回復義務を負わせるには「少なくとも、賃借人が補修費用を負担することとなる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項自体に具体的に明記されているか、仮に賃貸借契約書では明らかでない場合には、賃貸人が口頭により説明し、賃借人がその旨を明確に認識し、それを合意の内容としたものと認められるなど、その旨の特約(通常損耗補修特約)が明確に合意されていることが必要であると解するのが相当である」と判断しました。
平成17年判決の事案は「賃借人が住宅を明け渡すときは…負担区分表に基づき修補費用を賃借人の指示により負担しなければならない」という特約があった場合において、入居説明会が開催「すまいのしおり」も配布され、1時間半かけて契約条項の重要部分の説明等がされて、負担区分表の説明がされましたが、このような場合でも、原状回復費用に関する明確な合意がないと判断されました。
なお、平成17年判決の当事者は、賃貸人大阪府供給公社、賃借人一般人でしたが、消費者契約法施行の前の事案であったことに注意する必要があります。
イ 消費者契約法10条
次に、特約が、消費者契約法に違反しないということが必要になります。消費者契約法第10条は、消費者に不利な特約で、その程度が信義誠実原則に反する程度のものについては無効とすると規定しています。例えば、大阪高裁平成16年12月17日判決判時1921号61頁は、住宅の賃借人に通常損耗の原状回復費用を負担させる特約を消費者契約法10条に該当して無効であると判断しています。
参考になるものとしては、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン再改訂版」が示す、特約が有効と認められるための要件です。
① 特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること
② 賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること
③ 賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること
不動産関連の相談は、村上新村法律事務所まで
大阪オフィス
https://g.page/murakamishinosaka?gm
川西池田オフィス
https://g.page/murakamishin?gm
福知山オフィス
https://g.page/murakamishinfukuchiyama
交通事故専門サイト
https://kawanishiikeda-law-jiko.com/
投稿者:
不動産関連②賃貸業と改正民法・一部滅失等
2021.04.30

1 一部滅失等関連の改正民法の概要は、以下のとおりです。
民法611条
1 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。
2 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。
(1)1項に関する重要点は、下線に関する部分です。
改正前民法611条では「賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したとき」に、賃借人から賃料減額請求がされて初めて賃料が減額されるということになっていましたが、改正民法では、賃借人から減額請求をされなくても、当然に減額されるということになりました。
また、改正前民法は、賃料が減額される場合は一部「滅失」に限られていましたが、改正法では「その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合」として、賃料が減額される場合が拡大されました。この「その他…」については、どのような場合か明確ではなく、解釈に委ねられますが、典型例としては、水害で水浸しになって賃貸目的物が使用できないような場合が考えられます。
(2)2項に関する重要点は、同じく下線に関する部分です。
先ず「滅失」以外の場合は、1項の場合と同様、解釈に委ねられています。
次に1項と比較した場合「それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは」という文言がありませんから、借主に帰責事由がある場合でも、借主から解除できることになっています。この場合に貸主が被る不利益は、帰責事由ある借主が、債務不履行の一般原則に従って、損害賠償義務を負うという形で、回復されることになります。
2 一部滅失関連を契約書で定める場合の検討
民法の定めといっても、それが任意規定であれば特約(契約)によって修正できること、ただ、契約が行き過ぎると強行法規(公序良俗)に反し無効になることは、修繕関連で述べたとおりです。
ちなみに、標準契約書における一部滅失関連条項は、以下のとおりであり、その内容を説明します。
(一部滅失等による賃料の減額等)
第12条 本物件の一部が滅失その他の事由により使用できなくなった場合において、それが乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用できなくなった部分の割合に応じて、減額されるものとする。この場合において、甲及び乙は、減額の程度、期間その他必要な事項について協議するものとする。
2 本物件の一部が滅失その他の事由により使用できなくなった場合において、残存する部分のみでは乙が賃借をした目的を達することができないときは、乙は、本契約を解除することができる。
(1)重要点は、下線に関する部分です。
民法の規定では、一部滅失等の場合、当然に賃料が減額されるということになっていますが、修繕の範囲や修繕の期間などによって、一部減額する金額や期間に争いが生じうるところです。そこで、上記契約書では、民法611条1項を補完する形で、速やかな通知に基づいて借主と貸主が協議を行い、その協議によって解決を図るような定めとされています。
(2)なお、現実には、賃料を減額しなくても、一定期間賃料を免除するとか、代替物件を準備するとか、他の方法で借主が満足することも考えられます。そのような対応が可能かは「その他必要な事項」の中に含まれるかという解釈問題になりますが、より安全を図るのであれば、賃貸人としては「減額の程度」を「減額の要否、程度」とした方がよいと思われます。
3 一部滅失等とは
(1)一部滅失等とは、賃借物の物理的な破損だけでなく、設備の機能的な不具合等も含まれることは、改正民法が、賃料減額原因を「滅失」だけでなく「使用及び収益ができなくなった場合」にまで広げたことからも明らかです。
(2)旧法下の裁判例では、一部使用不能が通常の居住を不可能にするほどの状態かを重視する傾向にある(雨漏り部分を面積案分する等)とされていましたが、賃貸住宅管理業者に対するアンケート調査によれば、現場対応として「話し合い」を選択する率が70%を超えていました。それは話し合いの中で、賃料減額に限らず、謝罪、速やかな修繕等、適切な対応がなされてきたということを意味するのかもしれません。現場では、賃借物の使用収益についてトラブルが生じることは決して少ないということはなく、賃料減額原因の文言が拡大された現在、仮に裁判という段階にまでいけば、賃料減額が認められる場合はより増えるように思われます。
ですから、賃貸業者としては、問題が生じた場合は、賃借人と一層誠実に協議していくことが望まれるでしょう。賃借物を使用しているのは賃借人なので、現状は賃貸人にはよくわからないというのが本音でしょうから、賃借人に引き渡す前の段階で重要個所を写真で残しておく等、データを保管しておいた上で、いざ賃借人から修繕等の通知があったときは(これは賃借人の義務とされています、615条)、速やかに賃借物を訪問して現状を確認、今後の対応をスケージュールや費用も踏まえた上で具体的に協議すべきと思われます。
(3)ちなみに、トラブルの原因として多いものは(全てが、賃料減額原因となる訳ではないですが)、風呂が使えない、エアコンが作動しない、配水管の詰まり、上階からの漏水、雨漏りとなっています。
不動産問題の相談は村上新村法律事務所まで
大阪オフィス
https://g.page/murakamishinosaka?gm
川西池田オフィス
https://g.page/murakamishin?gm
福知山オフィス
https://g.page/murakamishinfukuchiyama?gm
交通事故専門サイト
投稿者:
緊急事態宣言とまん延防止等重点措置
2021.04.22
いずれも新型インフルエンザ等特別措置法(以下、特措法といいます。)を根拠としますが、主な違いを説明します。
まん防(まん延防止等重点措置)の根拠条文は、特措法31条の4です。その1項と2項では、以下のような定めがあります。ポイント部分に色付けしています。
第三十一条の六 都道府県知事は、第三十一条の四第一項に規定する事態において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある同項第二号に掲げる区域(以下この条において「重点区域」という。)における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該都道府県知事が定める期間及び区域において、新型インフルエンザ等の発生の状況についての政令で定める事項を勘案して措置を講ずる必要があると認める業態に属する事業を行う者に対し、営業時間の変更その他国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある重点区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するために必要な措置として政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。
2 都道府県知事は、第三十一条の四第一項に規定する事態において、当該都道府県の住民に対し、前項の当該都道府県知事が定める期間及び区域において同項の規定による要請に係る営業時間以外の時間に当該業態に属する事業が行われている場所にみだりに出入りしないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる。
他方、緊急事態宣言の根拠条文は、特措法45条です。その1項と2項には、以下のような定めがあります。ポイント部分に色付けしています。
第四十五条 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、当該特定都道府県の住民に対し、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間及び区域において、生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる。
特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間において、学校、社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。)、興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定する興行場をいう。)その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者(次項において「施設管理者等」という。)に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。
色付け部分を比較するとわかりやすいのですが、先ず、まん防が都道府県の「区域」に関するものであるのに対し、緊急事態宣言は都道府県「全域」に関わります(ただ、今回大阪府が実施したまん防の対象区域は「大阪府全域」でした。)。
次に、1項と2項の定める事項が逆転していますが、まん防が要請できるのは、特定の事業者に対する関係だけでその内容は「営業時間の変更」です。ところが、緊急事態宣言では、要請の対象が学校、社会福祉施設、興行場その他施設とはるかに広い上「当該施設の使用の制限」のみならず「停止」も求めることができます(要請等に違反した場合の過料も、前者は20万円以下、後者は30万円以下と異なります。)。
最後に、同じく1項と2項の定める事項が逆転していますが、まん防が住民に要請できるのは、上記事業者の事業所に「出入りしないこと」であるのに対し、緊急事態宣言では、住民の「居宅」等から「外出しないこと」です。
ちなみに、緊急事態宣言が対象とする学校、社会福祉施設、興行場その他の施設とは、以下のようなものです。同じく、今回話題の施設について色付けしています。
法第四十五条第二項の政令で定める多数の者が利用する施設は、次のとおりとする。ただし、第三号から第十三号までに掲げる施設にあっては、その建築物の床面積の合計が千平方メートルを超えるものに限る。
一 学校(第三号に掲げるものを除く。)
二 保育所、介護老人保健施設その他これらに類する通所又は短期間の入所により利用される福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設(通所又は短期間の入所の用に供する部分に限る。)
三 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学、同法第百二十四条に規定する専修学校(同法第百二十五条第一項に規定する高等課程を除く。)、同法第百三十四条第一項に規定する各種学校その他これらに類する教育施設
四 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
五 集会場又は公会堂
六 展示場
七 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣が定めるものの売場を除く。)
八 ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)
九 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場
十 博物館、美術館又は図書館
十一 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類する遊興施設
十二 理髪店、質屋、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗
十三 自動車教習所、学習塾その他これらに類する学習支援業を営む施設
十四 飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設(第十一号に該当するものを除く。)
十五 第三号から前号までに掲げる施設であって、その建築物の床面積の合計が千平方メートルを超えないもののうち、新型インフルザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等の発生の状況、動向若しくは原因又は社会状況を踏まえ、新型インフルエンザ等のまん延を防止するため法第四十五条第二項の規定による要請を行うことが特に必要なものとして厚生労働大臣が定めて公示するもの
- 大阪府において、令和3年1月に実施された緊急事態宣言では、飲食店が中心になっていましたが、今回4月に実施される緊急事態宣言では、百貨店等が対象になるかです。百貨店側としては、店舗でクラスター等は発生していないと反対していますが、大阪府としては、百貨店等を休業させることで、そこに到来する人数を減らした上で、結果として(街に出たついでに飲食等することを防ぎ)感染拡大を食い止めたいということのようです。
なお、兵庫県や京都府も大阪府と横並びで対応することになりましたが、例えば、梅田で百貨店が休業しているのに三宮で百貨店が開いてると、人の流れがそっちにいってしまうという点もあるのかもしれません。
法律問題は村上新村法律事務所まで
大阪オフィス
https://g.page/murakamishinosaka?gm
川西池田オフィス
https://g.page/murakamishin?gm
福知山オフィス
https://g.page/murakamishinfukuchiyama?gm
交通事故専門サイト
https://kawanishiikeda-law-jiko.com/
投稿者:
不動産関連①賃貸業と改正民法・修繕
2021.04.19

最近、村上新村法律事務所は、不動産業者の方とのお付き合いが増えていることから、不動産関連ブログを連載することにしました。手始めは、賃貸業と改正民法との関係について、若干。第1回目は、修繕に関する問題です。
1 修繕関連の令和2年改正民法の概要は、以下のとおりです。
(1)先ず、民法606条は、以下のとおり定めています。
1.賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
2.賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。
下線部が、令和2年改正民法による部分です。改正趣旨としては、改正前民法606条では、賃借人の責めに帰すべき事由によって賃借物の修繕が必要となった場合であっても、貸主が修繕義務を負担するのかどうか明確ではなかったので、貸主は修繕義務を負わないということを明確にしたということです。
(2)次に、民法607条の2が以下のとおり、追加されました。
賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。
一 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。
二 急迫の事情があるとき。
改正趣旨としては、改正前民法では、賃借人の修繕権限に関する明確な規定がありませんでした。解釈上、賃借人に修繕権限があるとの解釈がされていましたが、無条件に賃借人が修繕できるとすることも適当ではないため、賃借人が修繕できる場合を明確に定め、貸主と借主の利益の調整を図った規定ということになります。
2 修繕関連事項を契約書で定める場合の注意点
(1)ただ、改正民法606条、607条の2は任意規定として、特約による変更は可能とされています。
そこで、どの程度の修正が可能か問題になりますが、特約の内容が公序良俗に反する場合は民法90条により、あまりに賃借人に不利な特約は消費者契約法10条により、無効となる可能性あります。
(2)具体例による説明
ちなみに、国土交通省が提供する賃貸住宅標準契約書(以下、標準契約書といいます。)における修繕関連条項は、以下のようになっています。
(契約期間中の修繕)
第9条 甲は、乙が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければならない。この場合の修繕に要する費用については、乙の責めに帰すべき事由により必要となったものは乙が負担し、その他のものは甲が負担するものとする。
2 前項の規定に基づき甲が修繕を行う場合は、甲は、あらかじめ、その旨を乙に通知しなければならない。この場合において、乙は、正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒否することができない。
3 乙は、本物件内に修繕を要する箇所を発見したときは、甲にその旨を通知し修繕の必要について協議するものとする。
4 前項の規定による通知が行われた場合において、修繕の必要が認められるにもかかわらず、甲が正当な理由なく修繕を実施しないときは、乙は自ら修繕を行うことができる。この場合の修繕に要する費用については、第1項に準ずるものとする。
5 乙は、別表第4に掲げる修繕について、第1項に基づき甲に修繕を請求するほか、自ら行うことができる。乙が自ら修繕を行う場合においては、修繕に要する費用は乙が負担するものとし、甲への通知及び甲の承諾を要しない。
1項は、改正民法606条1項と同じことを述べています。
2項も基本的には改正民法と同様ですが、甲(賃貸人)としてはいきなり修繕費の請求をされても困るので、乙(賃借人)が修繕する際は前もって通知することを求めています。
3項の趣旨は、2項と同様で、甲保護の観点から、修繕前の通知と協議を求めています。民法607条の2号が求めているのは通知(+相当期間の経過)のみなので、協議は契約書で別途定める手続です。ただ、必要な修繕かどうかは、客観的なものとして、最終的には裁判所が決めるものなので「必要な修繕でない」という甲のゴリ押しを認めるものではありません。それは、4項が、正当な理由なく甲が修繕に応じない場合には、乙が修繕でき、また、その費用も1項に基づき甲に請求できる場合があることを定めていることからも明らかだと思います。乙自らが修繕する前に協議の場を踏むことで必要な修繕か否かに関する甲との紛争を事前に防止するものと解されます。
5項は、必要な修繕といっても、軽微なものに関しては、乙が自らの費用で負担し簡易な手続で修繕する方が合理的(賃貸目的物にも大きな影響を与えず、安価・迅速に済む)と考えられることから、民法607条の2の厳格な手続を排除するのと引き換えに、606条1項の例外を認めたものと解されます。
ちなみに、別表4で定めるものは、以下のようなものです。
畳表の取替え・裏返し、障子紙の張替え、ふすま紙の張替え
電球・蛍光灯・LED照明の取替え、ヒューズの取替え
給水栓の取替え、排水栓の取替え
その他費用が軽微な修繕
不動産の法律問題は村上新村法律事務所まで
大阪オフィス
https://g.page/murakamishinosaka?gm
川西池田オフィス
https://g.page/murakamishin?gm
福知山オフィス
https://g.page/murakamishinfukuchiyama?gm
投稿者:
まんぼう
2021.03.31
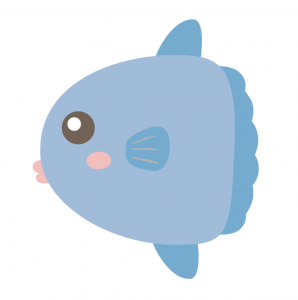
今日は、トピックスということで「まんぼう=まん延防止等重点措置」に関するお話です。
令和3年2月に改正され、新型インフルエンザ特別措置法(以下「特措法」といいます。)に追加された「まんぼう」に関する基本的な条文は、以下のとおりです。重要部分に、色付けしています。
(感染を防止するための協力要請等)
第三十一条の六 都道府県知事は、第三十一条の四第一項に規定する事態において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある同項第二号に掲げる区域(以下この条において「重点区域」という。)における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該都道府県知事が定める期間及び区域において、新型インフルエンザ等の発生の状況についての政令で定める事項を勘案して措置を講ずる必要があると認める業態に属する事業を行う者に対し、営業時間の変更その他国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある重点区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するために必要な措置として政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。
2 都道府県知事は、第三十一条の四第一項に規定する事態において、当該都道府県の住民に対し、前項の当該都道府県知事が定める期間及び区域において同項の規定による要請に係る営業時間以外の時間に当該業態に属する事業が行われている場所にみだりに出入りしないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる。
3 第一項の規定による要請を受けた者が正当な理由がないのに当該要請に応じないときは、都道府県知事は、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある重点区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため特に必要があると認めるときに限り、当該者に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。
4 都道府県知事は、第一項若しくは第二項の規定による要請又は前項の規定による命令を行う必要があるか否かを判断するに当たっては、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければならない。
5 都道府県知事は、第一項の規定による要請又は第三項の規定による命令をしたときは、その旨を公表することができる。
第八十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の過料に処する。
一 第三十一条の六第三項の規定による命令に違反したとき。
ポイントは、まん延防止措置が「特定の区域」ついてのもので(31条の6-1項)、要請対象が「事業者」及び「住民」になっていますが(同条1、2項)、要請よりも厳しい「命令」や「過料」の対象になっているのは事業者のみという点です(同条3項、80条1項1号)。
ちなみに、上記改正部分に関する特措法施行令は、以下のとおり定めています。
第五条の五 法第三十一条の六第一項の政令で定める措置は、次のとおりとする。
一 従業員に対する新型インフルエンザ等にかかっているかどうかについての検査を受けることの勧奨
二 当該者が事業を行う場所への入場(以下この条において単に「入場」という。)をする者についての新型インフルエンザ等の感染の防止のための整理及び誘導
三 発熱その他の新型インフルエンザ等の症状を呈している者の入場の禁止
四 手指の消毒設備の設置
五 当該者が事業を行う場所の消毒
六 入場をする者に対するマスクの着用その他の新型インフルエンザ等の感染の防止に関する措置の周知
七 正当な理由がなく前号に規定する措置を講じない者の入場の禁止
八 前各号に掲げるもののほか、法第三十一条の四第一項に規定する事態において、新型インフルエンザ等のまん延の防止のために必要な措置として厚生労働大臣が定めて公示するもの
31条の6-1項というのは、事業者(店側)に対する規定ですから、上記要請対象者が店側であることは明らかです。結果として、店側としては、マスクをしていない客の入店禁止を求められている訳ですが、その際に話題になっている「会食マスク」をどうするか、注目されるところです。
法律問題は、村上新村法律事務所まで
大阪オフィス
https://g.page/murakamishinosaka?gm
川西池田オフィス
https://g.page/murakamishin?gm
福知山オフィス
https://g.page/murakamishinfukuchiyama?gm
交通事故専門サイト
投稿者:
顧問弁護士④クレーム対応
2021.03.24

クレームの語源は「claim」という単語で、本来は要求・請求といった意味ですが、日本語的には苦情と理解されることが多いようです(いわゆる和製英語とされています。)。ですから、ここでは「商品・サービスに対し苦情を述べられた場合の対策」として話を進め、その中での弁護士・顧問契約の位置づけを説明したいと思います。
1 正当か不当か
苦情の中にも、本来的に不当なものと正当なものがあります。
例えば、スーパーの店員の態度が気にくわないとクレームを述べ商品を受け取ったにも関わらず代金を支払わないのは明らかに不当です。しかし、商品が痛んでいるからとクレームを述べ代金返還や交換を求めることは、本当に商品が痛んでいるのであれば正当です。ただ、その場合でも過度の損害賠償請求をすると不当になります。
また、例えば、引越しの際にグラスが壊れたこと自体、殊更問題視して、執拗に元に戻せと迫ることも不当です。グラスが壊れたことを悲しいと思っていることに共感を求めているのかもしれませんが、家族や友人ならまだしも契約の相手方にすぎない引越し業者にそれを求めることは、不当な要求です。壊れた物を元通りにすることは物理的に不能ですし、仮に、修復が可能であったとしても、1万円のグラスを30万円かけて修復するよう求めることは、社会経済的に不能を要求するものだからです。一時期話題になりましたが、土下座を求める構造と似ています。
ここではわかりやすい例を示しましたが、実際は、不当か正当かが不明確な場合や、両社が混在している場合などもあり、それらの判断は決して容易ではありません。この点をきちんと区別しないまま対応すれば、新たなクレームに発展したり、企業の信用を低下させかねません。他方、不当なクレームに安易に応じたことで、クレーマーが勢いづいたり、他の顧客からの同様の要求を誘引してしまったりということもありえます。
この点、弁護士であれば、クレームに対して、それらが法的に不当か正当かを判断し、適切に対応することができます。
2 弁護士による交渉
弁護士が企業の代理人としてクレーム対応することで、経営者・従業員の方は事業活動に専念することができます。相手が直接クレームを繰り返してきても、企業として基本的な対応(謝罪、交換、弁償等)をした後であれば、なすべきことは終えてるので「弁護士に連絡して下さい。」といえばすみます。
また、弁護士は交渉の専門家ですから、相手のクレームが悪質であったとしても、断固とした交渉を進めることができます。弁護士として刑事告訴や損害賠償請求等の法的手段について知らせることの効果は絶大です。
弁護士が電話したり、内容証明郵便で受任通知や警告書などを送付した途端に、相手からの連絡がなくなることは珍しくありません。
3 弁護士による法的対応
(1)刑事手続
相手方の行為がなんらかの犯罪に該当すれば、警察への告訴によって、刑事事件としてもらうことが考えられますが、警察がすべての事案を捜査してくれるというわけでもありません。
そこで、証拠を適宜収集・提出しながら、弁護士が、「告訴状」という形でクレーム行為について法的評価を加えた文書を作成し、警察や検察に相談することで、刑事事件として扱ってもらう方法があります。
(2)民事手続
金銭的なものでいえば、クレームについての損害賠償請求に対する防御、クレームの損害賠償についての債務不存在確認請求訴訟、進んで、クレーム行為に対する損害賠償請求があります。事実を告知すること自体、場合によっては名誉棄損、信用棄損にあたりますし、事実の中に間違ったことや不適切なことを織り込んでいれば、それは明らかに違法な行為です。
クレーム行為を止めさせるものとしては、仮処分手続があります。訴訟は判決に至るまで相応の期間を要しますが、それまでに仮処分手続によって裁判所から面談強要禁止の仮処分を出してもらえれば、法的には相手方からの押しかけや繰り返しの電話が止められます。また、この仮処分手続では、裁判所が相手方の言い分を聴く「審尋」というものが行われますが、その結果、相手方が納得し、クレーム消滅・和解ができることもあります。
(3)証拠収集
証拠は、事案に応じて様々なものがありますが、弁護士であれば、弁護士としての「職権」による収集が可能です。弁護士会を通じた弁護士法23条に基づく照会のように弁護士にしか用いることのできない強力な証拠収集方法もありますし、弁護士であれば、裁判所を通して行う調査嘱託や文書提出命令も的確に用いることができます。匿名、新設アカウントであれば、身元がバレないかといえば、そんなことはありません。
4 弁護士との顧問契約の必要性
(1)迅速対応
以上の対応に共通していえることは、迅速かつ的確な対応が大事だということです。
迂闊に交渉を進めてしまうと、思わぬところで相手方に弱みを握られることになりかねません。一度してしまった不用意な説明は、後から撤回・修正することが難しい場合があります。また、対応が遅ければ、それ自体がクレームの理由となったり、相手方を勢いづけたりすることにもなります。さらに、早期の段階で証拠を管理しておけば、後々の対応を円滑に進められます。
迅速かつ的確な対応をするためには、弁護士と顧問契約を交わし日頃から情報共有し、連携しておく必要があります。
顧問弁護士であれば、上記のような細かで手間のかかる数多くの対応もしてくれます。
(2)クレームの予防等
顧問弁護士は、クレームが発生する原因を少しでも減らすようにコンプライアンス体制の整備にも協力します。また、企業が顧問弁護士の存在をホームページやパンフレットで表明していれば、それだけでもクレームの予防になるでしょう。
当事務所と顧問契約を交わしていただければ、クレーム対策に限らず、各場面に応じて様々なサポートを提供しております。関心があれば、当事務所までご連絡ください。
顧問弁護士の相談は、村上新村法律事務所まで
大阪オフィス
https://g.page/murakamishinosaka?gm
川西池田オフィス
https://g.page/murakamishin?gm
福知山オフィス
https://g.page/murakamishinfukuchiyama?gm
投稿者:
ビフォア法人破産⑧支援協の再生計画案の内容
2021.03.09
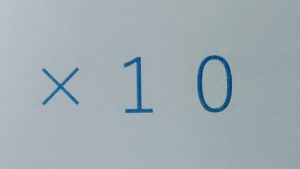
はじめに
中小企業再生支援協議会(以下、支援協といいます。)において、再生計画案の内容として記載すべき事項は、支援協事業実施基本要領(以下、要領という。)で定められています。
債権放棄の有無にかかわらず記載すべき事項(要領6(5)①~⑦)
(1)当該企業の自助努力が十分に反映されたものとして、①企業の概況、②財務状況(資産・負債・純資産・損益)の推移、③実態貸借対照表、④経営が困難になった原因、⑤事業再構築計画の具体的内容、⑥今後の事業見通し、⑦財務状況の今後の見通し、⑧資金繰り計画、⑨債務弁済計画、⑩金融支援(リスケジュール、追加融資、債権放棄等)を要請する場合はその内容を含むもの。
(2)金融支援を要請する場合は、その内容がリスケであろうと経営者責任の明確化を図る必要があります(要領6(5)⑤)。この点が事業再生ADRとの違いです。事業再生ADRでの役員責任は債権放棄を伴う場合にのみ不可欠とされています。他方、事業再生ADRでは責任の取り方が「退任」と明示されているのに対し、支援協では明確化が求められているに過ぎず、私財提供等でも足りるとされています。中小企業において役員を退任させると事業そのものが立ち行かなくなる場合もあるからです。
(3)権利関係の調整については、債権者間で平等であることを旨とし負担割合については衡平の観点から個別に検討されます(要領6(5)⑦)。
上記(1)⑤の事業再構築計画の具体的内容(要領6(5)②~④)
(1)再生計画案成立後最初に到来する事業年度開始の日等における以下の数値基準があります。
① 債務超過の状態にあるときは5年以内を目途に解消されること(但し企業の業種特性や固有の事情等に応じた合理的な理由がある場合にはこれを超える期間でも構いません。)
② 経常損失が生じているときは3年以内を目途に黒字になること(但し上記①括弧書の場合における同じ例外があります。)
③ 再生計画の終了年度(原則として実質的な債務超過を解消する年度)における有利子負債の対キャッシュフロー比率が概ね10倍以下となること(但し上記①括弧書の場合における同種の例外があります。)
(2)これを事業再生ADRと比較した場合、支援協では中小企業者のみを対象とするという特性から、上記①に関して事業再生ADRでは「3年以内」とされているのに対し支援協では「5年以内を目途」とされかつこの期間を超えることも認めています。上記②に関しても「3年」という点は同じですが、支援協では幅があるという点で上記①と同じです。上記③に関しては事業再生ADRでは触れられていない点です。
(3)債権放棄等の要請を伴わない再生計画案の場合には、数値基準を満たさない再生計画案の策定も許されます(要領6(5)⑨)が、それも中小企業者の特性等に配慮した点です。
債権放棄を伴う場合に記載すべき事項
(1)再生計画案が債権放棄等を要請する内容を含む場合は、上記1、2に加えて、破産手続による債権額の回収の見込みよりも多くの回収を得られる見込みが確実など債権者にとって経済的合理性が期待できることを内容として記載する必要があり、併せて支援協の個別支援チーム弁護士における内容の相当性と実行可能性が検証されることになります(要領6(5)⑧、6(6)①)。
(2)なお、この場合にも株主責任の明確化が求められています(要領6(5)⑥)が、その方法についてまでは示されておらず、事業再生ADRでは「株主権利の全部又は一部の消滅」と明示されているのとは異なっています。
事業再生・債務整理の相談は、村上新村法律事務所まで
大阪オフィス
https://g.page/murakamishinosaka?gm
川西池田オフィス
https://g.page/murakamishin?gm
福知山オフィス
https://g.page/murakamishinfukuchiyama?gm
事業再生・法人債務整理専門サイト
投稿者:
ビフォア法人破産⑦中小企業再生支援協議会
2021.03.01
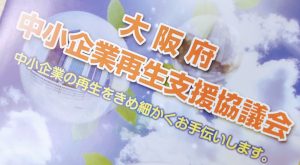
中小企業再生支援協議会とは
中小企業再生支援協議会(以下、支援協という。)とは、中小企業に対する再生計画策定支援等の再生支援事業を実施するため、産業活力強化法に基づき商工会議所等に設置される組織です。現在、全国47都道府県に1カ所ずつ設置され事業再生の専門家(弁護士、公認会計士、税理士、金融機関出身者など。)が常駐、日頃から中小企業者からの相談を受け付けています。
第一次対応
1 支援協の活動は、中小企業者(以下、当該企業という。)の申出を受け、企業内容の実体を把握しながら、事業再生に向けた相談に対し適切な助言等をする窓口対応から始まり、これを第一次対応といいます。
ここで中小企業者とは中小企業基本法2条にいうものです(①製造業・建設業・運輸業等-資本金額等〈以下、資と略〉3億円以下・常時使用従業員数〈以下、従と略〉300人以下、②卸売業-資1億円以下・従100人以下、③サービス業-資5千万円以下・従100人以下、④小売業-資5千万円以下・従50人以下)。
2 企業概要や3期分の税務申告書等を持参するのが通常で、併せて、現状に至るまでの経緯説明を1枚程度のメモに纏めていくと効率的な相談等が可能になります。
そこでのヒアリングの上、支援協を通じた再生支援の必要性と可能性が窺えるなら、当該企業の承諾を得て、次の第二次対応に移ります。その際、主要債権者(メインバンク)の意向確認が必要なので注意してください(中小企業再生支援協事業実施基本要領〈以下、要領といいます。〉6(2)①②)。
第二次対応
1 当該企業の再生計画の策定支援をするのが、第二次対応です。支援協では、個別支援チームが編成されます。
この段階で支払が継続されている場合には、債権額を確定等するため支援協と当該企業の連名で取引金融機関に対し一時停止の文書が送られます。規模の大きな事業者の私的整理を対象とする事業再生ADRという手続では、一時停止をする前の段階で、既にDDが実施され再生計画案の概要が作成されますが、支援協ではその後にDDをすることが予定されています。それは、支援協の対象が中小企業者であり独自で専門家を見つけ出し依頼することは難しく、支援協が関与する前の段階でそこまで求めることは酷であろうと考えられたためです。
(2)再生計画の内容は要領で決まっており、事業財務状況の見通しをたてなければなりません(6(5)①)。
迅速かつ簡易な再生計画の策定支援でない限り、外部専門家(公認会計士、税理士、中小企業診断士等)を含む個別支援チームが編成されますが、当該企業が実施したBS・PL等の財務DDと事業DDで状況把握可能なら、外部専門家等がそれを検証する形で、再生計画案の作成支援がなされます(要領6(3)①、(4)④)。
(3)このようにして支援策定された再生計画案について、支援協は、その内容・実行可能性・金融支援の必要性・合理性等に関する調査報告書を作成します(要領6(6))。
以上を元に債権者会議等により全金融機関の合意が得られれば、再生計画は成立します(要領6(7))。
モニタリング
第二次対応により成立した再生計画について、当該企業の決算期も考慮しながら必要な時期を定め、その達成状況等を監督していきます。その期間は、概ね3事業年度とされていて、その間必要性が生じれば再生計画の変更にも支援協力していくことになります(要領8)。
事業再生・法人債務整理の相談は、村上新村法律事務所まで
大阪オフィス
https://g.page/murakamishinosaka?gm
川西池田オフィス
https://g.page/murakamishin?gm
福知山オフィス
https://g.page/murakamishinfukuchiyama?gm
事業再生・債務整理専門サイト
投稿者:
ビフォア法人破産⑥私的整理の金融支援方法
2021.02.21
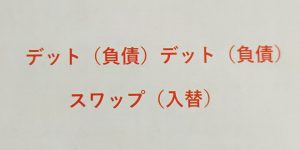
はじめに
私的整理とは、債務支払に関する交渉ですが、その対象は金融機関等のみで、如何なる金融支援がどの程度必要かが、検討されます。以下では、リスケの外、DDS、DES、債権放棄といった金融支援の方法を検討しますが、金融支援を受ける場合は、貸出条件緩和債権に陥って格下げを受けないよう、実抜計画・合実計画等に基づき行うことが必要です。
金融支援方法
1 リスケジュール
リスケジュール(以下、リスケという。)とは、元本或いは利息の支払期限等を繰り延べることをいいます。金融機関への支払を繰り延べることで、その分の金員をプールして運転資金を増やし、経営が落ち着いた段階で金融機関に対する支払を再開するものです。私的整理では、全員一致というハードルもあるせいか、このリスケで終わることが大半です。
2 DDS
DDSとは、Debt Debt Swap(デット・デット・スワップ)の略であり、債権者が既存債権を別条件債権に変更することをいいます。金融機関が既存の債権を他の債権よりも期間、利息等で劣後するものに切り替えて行うのが一般的です。債権の格付け査定上、劣後借入金が自己資本に算入されることから、債務超過解消要件を満たすことができない案件ですが、債権放棄にまで至らない案件に使われるスキームです。
債務者としては、実質純資産額の改善にはなりませんが、元金の返済が猶予され金利も引き下げられるので、貸出金利が高い時代は、キャッシュフロー改善のメリットが意外と大きいです。なお、金融機関次第ですが、流行していたころのDDSを見渡すと、返済猶予の期間は5~10年、利率0.4~0.8%程度にされることが多いようでした。金融機関としては、債権がなくならないという意味で、債権放棄や後述のDESよりもインパクトが少ないです。DDS化した債権については100%の貸倒引当金が求められるのが一般的で、その支援を受けるハードルは低いとはいえませんが、一時、中小企業に対する金融支援策としては注目された手法でした。
3 DES
DESとは、Debt Equity Swap (デット・エクイティ・スワップ)の略で、債務を株式化することです。金融機関が債権の一部を現物出資する形で(償還)株式等を取得し切り替える方法が一般的です。これによって金融債務が減少し債務者の財務状態は改善されます。後述する債権放棄には限界があり、それでも不十分な場合の追加金融支援策としての利用が考えられます。
一応株式化されるので、債権放棄程の衝撃性はありませんが、それに伴うメリットも受けられません。また、たとえそれが償還株式であったとしても、法的には債権を失う訳で、いざという場合特に上場していない債務者についてその回収は困難です。また、金融機関である以上独禁法上の限界もあります。そのため、利用例は少ないように思います。
4 債権放棄
債権放棄とは、金融機関等がその債権を放棄することです。金融機関にとって最も厳しい支援であり、その調整に時間と手間を要します。
債権放棄を行う場合、金融機関では欠損金処理が、債務者では債務免除益課税が、それぞれ問題になります。併せて、金融機関にとって、債権放棄という痛みを伴う支援ですから、そのような事態に陥ったことについて債務者の説明責任、経営者責任、株主責任が問われて当然であり、オーナー経営であったのなら私財提供も問題にされます。
その上で、債権放棄の必要性と相当性、経済的合理性、各金融機関の衡平性、過剰支援となっていないか等が検討されます。なお、その上限は、一般的に、実質債務超過額、非保全額、税務上の欠損金の何れか小さい金額であり、これを超える放棄は過剰支援として合意を得ることは難しいことが多いと思われます。
法人破産・私的整理の相談は、村上新村法律事務所まで
大阪オフィス
https://g.page/murakamishinosaka?gm
川西池田オフィス
https://g.page/murakamishin?gm
福知山オフィス
https://g.page/murakamishinfukuchiyama?gm
事業再生・債務整理専門サイト
投稿者:
ビフォア法人破産⑤実抜計画・合実計画・暫定リスケ
2021.02.15
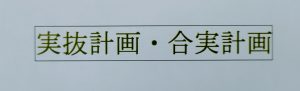
DSC_0649
実抜計画
1 事業再生を前提とした金融負債のリスケ等は「貸出条件緩和債権」として債務者区分を格下げされないようにしなければなりません。さもないと、事業再生に必要な追加資金融資を後日受けられなくなるからです。
実抜計画とは、実現可能性の高い抜本的な経営再建計画をいいます。金融庁の監督指針(以下、監督指針といいます。)Ⅲ-3-2-4-3(2)③ハが指摘するもので、その計画に基づく経営再建が開始されている場合には、リスケをしたとしても「貸出条件緩和債権」には該当しないとされています。
私的整理では、かかる実抜計画等に基づく経営再建が出来るかが重要になります。
2 実抜計画といえるには、先ず「実現可能性の高い計画」である必要があり、それは、①必要関係者との同意が得られていること、②支援の額が確定しており追加的支援が必要と見込まれないこと、③売上高、費用及び利益予測等の想定が十分に厳しいものになっていることを全て満たす計画です。
続いて、実抜計画といえるには「抜本的な計画」である必要があり、それは「概ね3年後の当該債務者の業況が良好であり、かつ、財務内容にも特段の問題がないと認められる状態となる」計画です。従前は「概ね3年後の当該債務者の債務者区分が正常先となった場合」とされていましたが、令和元年12月の金融検査マニュアル廃止に伴う監督指針の改正により内容が変更されました。
合実計画
1 合実計画とは、合理的かつ実現可能性の高い経営改善計画をいいます。それは、監督指針Ⅲ‐3‐2‐4‐4③が指摘する概念で、本来的には当該債務者の債務者区分を要管理債権又は正常債権に格上げするためのものです。ただ、監督指針Ⅲ‐3‐2‐4‐3(2)③ハ(注2)では、債務者が中小企業であれば、合実計画が策定されている場合には、実抜計画と「みなして差し支えない」とされているので、中小企業の事業再生では、とりあえず合実計画の策定を目指すことになると思います。
2 ちなみに、監督指針の示す合実計画の主な内容は、以下のとおりです。
① 経営改善計画等の計画期間が原則として概ね5年以内で、かつ、計画の実現可能性が高いこと
ただし、計画期間が5年を超え概ね10年以内となっている場合で、進捗状況が概ね計画どおり(売上高・当期利益が事業計画に比し概ね8割以上確保されていること)であり、今後も概ね計画どおりに推移すると認められる場合を含む。
② 計画期間終了後の当該債務者の業況が良好で、かつ、財務内容にも特段の問題がないと認められる状態(自助努力により事業の継続性を確保することが可能な状態となる場合は、金利減免・棚上げを行っているなど貸出条件に問題のある状態、元本返済若しくは利息支払いが事実上延滞しているなど履行状況に問題のある状態のほか、業況が低調ないしは不安定な債務者又は財務内容に問題がある状態など今後の管理に注意を要する状態を含む。)となる計画
③ 全ての取引金融機関の経営改善計画等に基づく支援の合意があること
ただし、単独で支援を行うことにより再建が可能な場合等は、当該金融機関の合意で足りる。
④ 金融機関等の支援の内容が、金利減免、融資残高維持等に止まり、債権放棄、現金贈与などの債務者に対する資金提供を伴うものでないこと
暫定リスケ
1 以上のとおり、私的整理の原則は、実抜計画・合実計画を策定して全金融機関等との合意形成に向かって話し合いをしていくことになります。つまり、完済計画による話し合いということです。
2 しかし、このような完済計画を立てる前段階として、そもそも事業の持続可能性が不透明な債務者については、その可能性が見込めるかどうか、今後経営改善や事業再生が実現できるかどうかを、あらためて熟慮する期間が必要な場合もあります。
そこで、金融円滑化法(以下、円滑化法といいます。)が廃止される平成25年4月以降の方針として、中小企業再生支援協議会を通じて、1~数年間はリスケを前提に弁済方法を暫定的に決定し、その後の弁済方法は更新時の経済状況を踏まえて改めて協議するという方式が認められていました。これが正式な「暫定リスケ」といわれる方式で、3年計画を基本としたモニタリングを通じて、実抜計画・合実計画の策定等を模索するというものでした。
3 ところが、現実は、円滑化法廃止後も、多くの金融機関はリスケに寛大であったため、相対型の私的整理においても、暫定「的」リスケが続けられ、それは現在のコロナ禍リスケの流れに続いています。
事業譲渡
なお、実抜合実計画・暫定リスケを越えて、事業再生のための事業譲渡を考える場合は、こちら
事業譲渡の意義 https://m2-law.com/blog/2053
事業譲渡と会社分割 https://m2-law.com/blog/2124
事業譲渡と第二会社方式 https://m2-law.com/blog/2137
事業譲渡と民事再生 https://m2-law.com/blog/2220
事業譲渡と破産手続 https://m2-law.com//blog/2408
法人破産を考える前に
事業再生・私的整理の相談は、村上新村法律事務所まで
大阪オフィス
https://g.page/murakamishinosaka?gm
川西池田オフィス
https://g.page/murakamishin?gm
福知山オフィス
https://g.page/murakamishinfukuchiyama?gm
事業再生・債務整理サイト
投稿者:
ARTICLE
-
不動産
-
事業再生法人破産
-
企業法務
-
新着情報
SEARCH
ARCHIVE