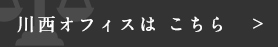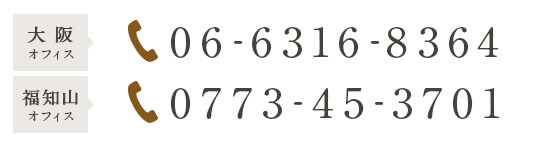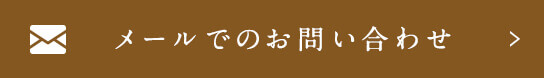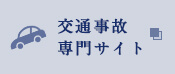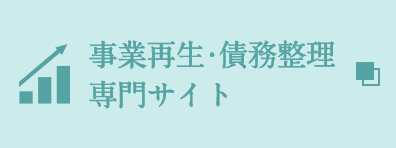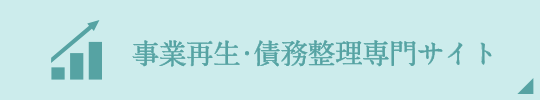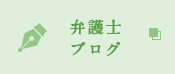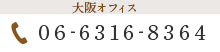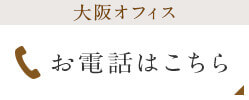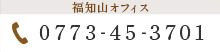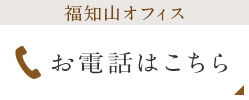- HOME
- 企業法務
競業避止義務⑤FC本部の基礎知識
2025.10.06
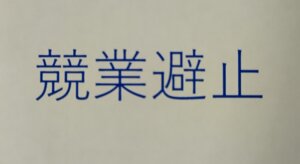
DSC_9951
第1 はじめに
1 競業避止義務の意義
競業避止義務とは、事業者と一定の関係にある者が、その事業者と競業する関係に立たないようにする義務のことを競業避止義務と言います。[1]
2 発生根拠
フランチャイジー(以下、「ジー」といいます。)の競業避止義務はどのような場合に発生するのでしょうか?
⑴ 一般論としての競業避止義務は、取締役や支配人のように法律で定められたもの(商法16条、23条、28条、会社法356条、365条、594条)のほかに、当事者間の契約で定められたものや信義則上認められるものなどがあります。
⑵ フランチャイズ契約(以下、「FC契約」といいます。)の場合には、商法や会社法などの法律が存在しないので、契約期間中及び契約終了後の競業避止義務については合意を定めることにより発生します。したがって、フランチャイザー(以下、「ザー」といいます。)としては、合意で競業避止義務を定めることが重要になります。[2]実際に、ほとんどのFC契約では契約期間中の競業行為が禁止され、さらに、契約終了後も一定期間営業行為が禁止される例が多いです。[3]
仮に、合意で禁止していない場合、競業避止義務は存在しないとも考えられますが、契約終了後の競業避止義務の存否が問題となった事案ではありますが、合意がなくともジーに信義則上の競業避止義務を認めた裁判例が存在します。[4]
3 ジーの競業避止義務
⑴ 上述した通り、ジーの競業避止義務は合意を根拠に発生するものと信義則を根拠に発生するものがありますが、本稿では前者の競業避止義務について取り上げることにします。
⑵ 合意を根拠に発生する競業避止義務の問題は契約期間中と契約終了後の競業避止義務に分けて考えるべき[5]ところ、本稿では契約終了後の競業避止義務の有効性について検討します。
第2 契約終了後の競業避止義務条項の有効性
1 ザーが競業避止義務を設ける理由は、①「ザーの商権の保護ないし商業圏の確保」、②「ノウハウの保護」、③「消費者がザーの営業と混同することの防止」に求められます。他方で、契約終了後の競業避止義務はジーの職業選択の自由ないし営業の自由を制約するだけでなく、ジーの生存権をも脅かす可能性があります。[6]
2 そこで、合意によって競業避止義務があったとしても、契約終了後の競業避止義務の内容がジーにとって過度の制約にわたる場合には、当該競業避止義務を定めた合意が公序良俗(民法90条)に反し無効となります。[7]公序良俗に反するかどうかについては、一般的に⑴禁止される業務の範囲(後述東京地判平成21年3月9日参照)、⑵禁止される場所、⑶禁止される期間[8]の3点において過度に広範な制限に当たらないかどうかによって判断されます。[9]
3 もっとも、競業避止義務の内容が上記⑴~⑶の基準は一応の形式的なものと思われ、実質的な考察が必要と解されます。すなわち、最終的には競業避止義務を認める必要性と競業避止義務を認めることによって生じる不利益(「加盟店側の投下資本の回収ができなくなる」、「生活が奪われる」などの重大な不利益をここでは想定しています。)の程度を比較衡量したうえで、競業避止義務の適用がみとめられるか判断せざるを得ないでしょう。
裁判例を見てみると、①FC契約終了後直ちに、②同一の営業を、③同一の場所で営んでいる場合には、競業避止条項が有効として差止めを認めているものが多いと思われます。他方で、①~③全てを充たすような場合でも差止めを認めない場合もあるように思われます。
例えば、以前から「〇〇」パン屋として営業していた者がジーとしてザーの商号・屋号である「××」パン屋として営業をした後、FC契約終了後ただちに、再度「〇〇」パン屋として同一の店舗で営業を継続する場面[10]を想定します。この場合には、①FC契約終了後直ちに、②同一の営業を、③同一の場所で行っているため、差止めが認められそうにも思われます。しかし、ジーはFC契約締結前にパン屋を営業しており、その時期に独自の商圏を構築しているため、競業避止義務が課されるとジー独自の商圏が奪われるという不利益を被ります。加えて、ジーが構築した商圏ともいえる以上、①「ザーの商圏の保護ないし商業圏の確保」という競業避止義務を設ける理由が妥当しません。それゆえ、上記のようなケースにおいては、ジーに競業避止義務を課すべきではない場合もあるのかもしれません。
また、例えば、自宅を改装してジーとして経営を行っていた者が、①FC契約終了後ただちに、②同一の営業を、③自宅で継続する場合も競業避止義務を課すべきかにも迷いはあります。なぜならば、改装された自宅を再改装するにも多額の費用を要する場合があるでしょうし、生活の拠点である自宅から退去することにより生存権をも脅かされる事態になりかねないからです。裁判例でも、期間前解約の事案(H16・12からの6年契約をH20・6に解除)について「洗車機等の設備は本件土地上に定着しており、これをほかの土地に移設することが可能であるとしても多額の費用(初期投資2400万円、設備リース料が月60万円×72か月)が必要になることが認められ、これらの事実からすると、原告(ジー)が本件土地上での洗車場の経営を禁止されることにより被る不利益は大きいものと認められる」と述べたうえ、「原告に競業避止義務を負わせて投下資本の回収を困難にすることは、信義則に反し許されない」として差止めを認めなかったものがあります。[11]
第3 東京地判平成21年3月9日・判時2037号35頁[12](競業避止義務は無効)
1 事案の概要
FC契約の対象となる事業は労働者派遣事業でした。FC契約では「契約期間満了後の二年間はXの事業と同種又は類似の事業を営んではならない」旨の競業避止義務が定められていました。それにもかかわらず、加盟期間(加盟期間の合計は6年:平成11年3月~平成17年3月末)が終了した加盟店を吸収合併した被告は加盟店の雇用していた技術者をそのまま利用して同一の労働者派遣事業を行いました。
2 判示事項
「コンビニエンスストア、ファーストフード、ファミリーレストランのように統一的ないし定型的な商品の仕入れないし製造、販売する業態においては強い従属性が認められるが、本件フランチャイズ事業は……個々の派遣内容ごとに内容の異なるサービスを提供する事業であり、サービスの定型化の程度は低く、営業成績も必然的にジー独自の信用・企業努力に左右される」とした上で、加盟店が「経営ノウハウの中核部分を使用しているとは認められないこと」や競業禁止によって「ジーは……営業の自由及び職業選択の自由が全面的に制限される」ことを認定している。そのうえで、「本件競業避止規定の制限内容は、競業禁止により保護されるザーの利益が競業禁止によって被る旧ジーの不利益との対比において、社会通念上是認し難い程度に達しているというべきであり、公序良俗に違反して無効である」と判断しました。
3 裁判例に対する考察
本件裁判例はFC契約の対象事業が労働者派遣事業であり、ザーよりもジー独自の信用・努力に左右されることを重視して、競業避止条項を無効としました。
従来の裁判例では、競業避止義務の履行を求めて差止請求をしたり、競業避止義務の不履行による違約金を請求したりすることは信義則に反し許されないとした例(ザーの勧誘に問題があったと認められるもの、東京高判平成21年12月25日・判時2080号41頁[13]や前掲大阪地判平成22年5月12日[14])はあります。しかし、FC契約の対象事業に着目して競業避止義務を認めなかった裁判例は見受けられませんので、非常に興味深い裁判例であるといえます。
もっとも、このような裁判例が存在する以上、ザーとしてはフランチャイズの対象となる事業の種類によっては、ジーに競業避止義務を課したとしても拘束力が否定される可能性もあることを念頭に置いてFC契約を締結する必要があります。なお、労働者派遣事業以外のいかなる業種に対して、本件裁判例の趣旨が及ぶかについては重要な検討課題といえるでしょう。
以上
[1] フランチャイズ契約の実務と書式(改訂版)P.178参照
[2] 【取引法研究会レポート】「フランチャイズ契約における競業避止義務」三島徹也P.81~82参照
[3] フランチャイズ契約の実務と書式(改訂版)P.178参照
[4] 東京高等裁判所平成20年9月17日決定・判例時報2049号21頁(契約終了後の競業避止義務について、黙示の合意の存在は認められないとしたが、「契約終了後の競業避止義務が全くないとすれば、」「原告が築いた無形の財産の保護にも欠けることとなる」等の理由から「契約に付随する義務として、信義則上」「一定期間の競業避止義務を負うものと解するのが相当」であるとした事案)参照
[5]「フランチャイズ契約における競業避止義務」大山盛義 沖縄法政研究第8号(2005)P.131参照
[6]【取引法研究会レポート】「フランチャイズ契約における競業避止義務」三島徹也P.81参照
[7] ただ、ザーにとって事業はFC契約の対象として重要な存在であり、事業者間との合意でもあることから、取締役や従業員の競業避止義務とは別に考える必要があると思われます。
[8] 東京地判令和3年1月25日・判例秘書掲載(インテリアリペアを含む総合カーリペア事業を対象とするFC契約の「契約終了後の10年間は本部からノウハウ教示を受けた事業並びにこれに類似する事業又は商品の取り扱いを行ってはならない」旨の規定の有効性が問題となった事案)は、本件競業避止条項は3年間の限りで有効性が認められるのであり、これを超える期間、超える範囲の競業禁止条項部分は公序良俗に反して無効というべきであると判断しました。したがって、3年以上の期間を合意により設定しても、差止めをすることができない可能性があります。
[9]フランチャイズ契約の実務と書式P.183 Question59参照
[10] 既に事業を行っている同業者とFC契約を締結して組織化する類型は「コンバージョン型フランチャイズ」と言われています。典型例は、センチュリー21です(フランチャイズにはどんな種類があるの?それぞれの特徴や違いを解説 [フランチャイズで独立] All About参照)。
[11] 大阪地判平成22年5月12日・判時2090号50頁
[12] 「フランチャイズ契約終了後における競業避止義務に関する判例分析と考察」波光巖(神奈川法学第44巻第1号 P.156~158参照)
[13] 当該裁判例は、ザーが詐欺的行為によってFC契約の締結をジーに勧誘し、ザーとしての経営指導を行わず、ジーがノウハウをほとんど受けていないという経緯があったことから信義則違反を肯定した。(BUSINESS LAW JOURNAL 2015.4「フランチャイズ契約のトラブル防止・対応策」P.93図表3参照)
[14] 当該裁判例は、①店舗の開設、運営のために多額の費用を投じていることなどからすると、ジーが営業を禁止されることにより被る不利益は極めて大きかったこと、②ザーが、ジーに代わって自ら又は他のジーをして店舗又はその近隣で運営することを現実に予定しておらず、店舗の商圏を維持しなければ、ザーが重大な不利益を受けるとはいえないこと、③ジーが本件店舗に多額の費用を投資したことは、ザーによる情報提供義務に違反する勧誘行為が契機となっていたことから信義則違反を肯定した。(前掲BUSINESS LAW、P.93図表3参照)
フランチャイズ本部・FC本部の相談は、弁護士法人村上・新村法律事務所まで
大阪オフィス
https://g.page/murakamishinosaka?gm
川西池田オフィス
https://g.page/murakamishin?gm
福知山オフィス
投稿者:
ARTICLE
-
不動産
-
事業再生法人破産
-
企業法務
-
新着情報
SEARCH
ARCHIVE